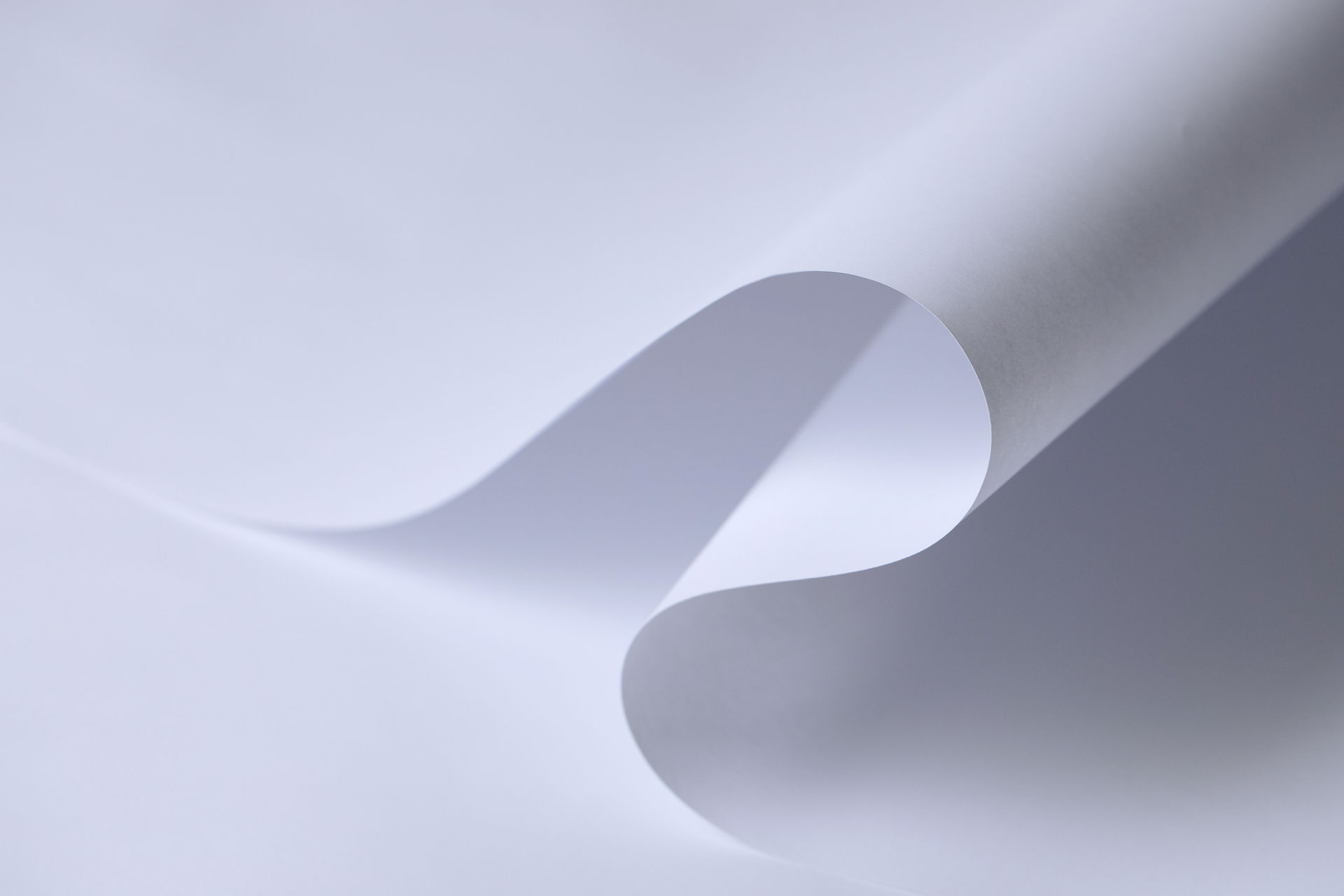
日々の泡
文学雑感
小林秀雄
小林がモーツァルトを書いたきっかけは、東京の女から逃げて、詩人を避けて、ヤクザな観念で道頓堀を歩いていた時に聴いたモーツァルトだよね。
吉川英治「新・平家物語」全20巻、読了
若き日と、これで2回目だが、初夏から今日まで流石に時間が掛かった!
だが、再発見、この作家の人間心理の詩的言語表現の美は三島由紀夫の筆に、風景四季を歌う筆致洞察力の妙は泉鏡花の言語に比して優るとも劣らず、構成、エンタテインメント、大衆文学を真の国民文学足らしめる、足掛け7年に及ぶ傑作である事を再発見し、新しい喜びが得られた。
純文学などを気取る現代の若手小説家諸君や、その稚拙な文章力に熱を上げている読者は、是非この作家に学ぶべし。時あらば、ノーベル文学賞はこうした作家に与えれれるべきと思う。
さて、その吉川英治が文化勲章を辞退しようと思っていたのを、文学の鬼たる評論家の小林秀雄が訪ね、貴方が受けるべきだ、それが読者の喜びなのだと口説いたという話が残っているが、ドストエフスキーと格闘し、論じていた小林の眼には、大衆文学者吉川英治こそ文化の勲章を得るべき作家と映っていたのであろう。
さて、3回目の「三国志」読書に、次はいつ挑戦できるかな?
(2017年11月)
立原道造 「盛岡ノート」
朗読の材料を探していたら、川上澄生や谷中安規などの版画本に混ざって、立原の「盛岡ノート」の復刻版が出てきた。装丁は道造と交友関係にあった画家の深沢紅子とある。
10年前、東北の温泉に一人旅して盛岡の光原社で手に入れたのかも知れない。ここは賢治の「注文の多い料理店」を出した本屋の跡地である。
懐かしくパラパラめくっていたら、この本で盛岡放送のアナウンサーたちが朗読劇をやったと言う記事がしおりに書いてあり、益々興味が湧く。
夭折の詩人立原道造は死の前年、最愛の人水戸部アサイと年少の友人中村真一郎に見送られて上野から北への旅に出た。ゲーテが愛人シュタイン夫人に「イタリア紀行」を綴った様に、道造はアサイへの想いを持ってこの一冊を書き上げた散文詩である。帰京後、第一回中原中也を受賞するも、翌月他界した。
彼は、夏の涼風である。その例として一編
アダジオ
光あれとねがふとき
光はここにあった!
鳥はすべてふたたび私の空にかへり
花はふたたび野にみちる
私はなほこの気層にとどまることを好む
空は澄み雲は白く風は聖らかだ
アルチュール・ランボー雑感
彼のことは18歳の時、小林秀雄の論文「人生の折断家ランボー」で知った。そして岩波文庫の「地獄の季節」(小林秀雄訳)を読み耽った。
パリのセーヌ左岸の本屋でランボーの原文と英訳の詩集を見つけ、帰国して小林の訳で当てはめたら全然違ってた。だが粟津潔や金子光晴の正当な訳と言われる物はもうランボーではなかった。小林は肉体でランボーを読み、文法では読まなかったと思った。僕はそのそうした小林にランボーを見出した。
名前がいいよね。アル中乱暴!だって。
ルックスがいい!詩人は顔である。
ボードレール、コクトー、金子光晴、中原中也、朔太郎、みんな顔がいい。顔の悪い奴はどこか詩もダメだ。
鎌倉の田村隆一宅で午前中から深夜まで飲み続けたことがあるが、アル中の顔がいいので飽きなかったなぁ。
詩という言葉が顔を刻むのだ。顔の悪い詩人は詩という彫刻刀とまだ出会っていないのだ。例えば谷川俊太郎や画廊巡りしてばかりいる詩人は口が偉そうでも顔が成立していない、 作詞家の秋元康などはもうブスの部類。
さて、ランボーは詩というより散文詩人であった。たった二冊の小品「地獄の季節」「イルミナシオン」を残しただけだ。世界を震撼させる爆薬はたった二個だけだった。これは永遠の爆弾だった。
詩論など書かなかった事が、詩人だ。また、彼はいつも過去からでなく、未来からみた今日の自分の在りようを描いていた。それが詩人と言うものだ。詩人は過去の迷信や間違った宗教を唾棄する真の宗教的予言である。
詩とポエムは違う。
フランスではポエムとはセンチメンタルなロマンチックの意であった。
彼は年長のヴェルレーヌをそうしたポエムから脱却させようと二人で旅に出た。
だが、ヴェルレーヌはランボーのような無神論者にはなれなかった。
ランボーは道で酒とパイプとパンを友としたが、ヴェルレーヌは高級レストランをいつも居間とした。食い物とワインの話に巧みな男は、本当のダンディズムを知らない小金持ちに多い。
真のダンディズムとは、野生と革命の孤独と痛みを隠し持った者の蓑笠である。
行動が詩になる事。遂に彼は文字を捨て、行動家になった。
詩作、僅か二年。パリで燃焼し、パリを捨てた。ヴェルレースは女になってしまい彼を手にした拳銃で撃った。嫉妬の弾は、近代と現代の別れ道になり、ランボーの指を掠めただけだった。彼は女の元を去った。パリを捨てた。彼の詩は近代史の革命碑になったが、その後の彼のとった行動は不明な砂漠の風塵である。アフリカやアラブの太陽と砂が彼を刻んだ事だろう。きっと詩人よりいい顔になっていたと思う。
彼は叫ぶ。
「見つかった!何が、永遠の太陽が!」
では、センチメンタルは詩にならないか?
だが、彼も太陽を求めながらも、最後には「別れ」を歌うのだ。
「もう秋か、それにしても何故に
その頃、やっと我が国では青年の富永太郎が、小林秀雄が、中也が放浪のランボーと言う危険なロックミュージックを待っていたのである。
澁澤龍彦展
実に几帳面な、真摯な研究家である。彼の残した幅広い著作を網羅するには大変な努力がいると思いながら会場を巡った。
そして、澁澤は時代の流行作家にはなり得ないが、永遠の流行作家であると言う思いが湧いた。即ち、こちらが求めてページを捲れば、飽きることのない知性の相談者になってくれる美学者であると言う事だ。
氏が愛好したパイプの写真があった。銀座菊水によく通っていたと言うが、自分もそこで買い、今持っているパイプと全く同じものをその中に見つけ、思わずニヤリとした。パイプには人それぞれの嗜好があり、人がどんなパイプを好んでいるかは興味の湧く所であるからだ。
氏と交友のあった四谷シモンさんの新版「人形作家」があったので買い求め、芦花公園で夕陽見ながら煙をふかした。
2017年12月17日まで、世田谷文学館
寺山修司
久々に母校に行った。
「いまだ知られざる寺山修司展」(同学部同学科で10年先輩だった彼)を昨年から今日まで早稲田の大隈記念タワーで開催していたからである。早大学生時代から天井桟敷旗揚げまで、若かりし頃の寺山の創作に光を当て、母校に寄贈された寺山未公開資料が展示された大変興味深い展覧会であった。(写真は大隈講堂が見える窓に映し出された若き寺山像を撮影)
でも、現役の見学学生はほとんどいなかった。
さて、展覧会の隣の大隈講堂では、丁度、その寺山の天井桟敷設立に東由多加等と関わった映像作家安藤紘平教授の最終講義が開かれていた。(安藤氏はTBSを退社後早稲田で教鞭をとっていたのだが)その内容は・・リレー対談で
第一部 「私と寺山修司」
ゲスト 篠田正浩監督 九條今日子、萩原朔美
第二部 「私と映画」
ゲスト 山田洋次監督 大林宣彦監督 奥田瑛二
第三部 「私と音楽」
ゲスト 山崎ハコ 谷川賢作
この面々、どんな話が飛び出すかと期待をもって聴講したが、時間制約のせいか、これがまったく面白くも可笑しくもない薄っぺらで終ってしまったので、落胆した。
そこで、展示されていた寺山の言葉、胸に残ったものを書いておく。
「ぼくはむしろ養いつづけてきた瞑想へのひとつの到達として、一切の諸科学の鳥を超え、地位や権力よりももっと高み彼方のあるものになりたいと思っていた。
それは『質問』であった。
ぼくは『大きくなったら、質問になりたいのです!』」寺山修司
「うまく質問するのは、なかなか難しい。問題がなければ質問しないわけだが、その問題が間違っていたらしようがないでしょう。うまく問題を自分で拵えて、質問をしなければいけない」略「実際、質問するというのは難しいことです。本当にうまく質問することができたら、もう答えは要らないのですよ。(中略)僕はだんだん、自分で考えるうちに、『おそらく人間にできるのは、人生に対して、うまく質問することだけだ。答えるなんてことは、とてもできやしないのではないかな』と、そういうふうに思うようになった。」小林秀雄
