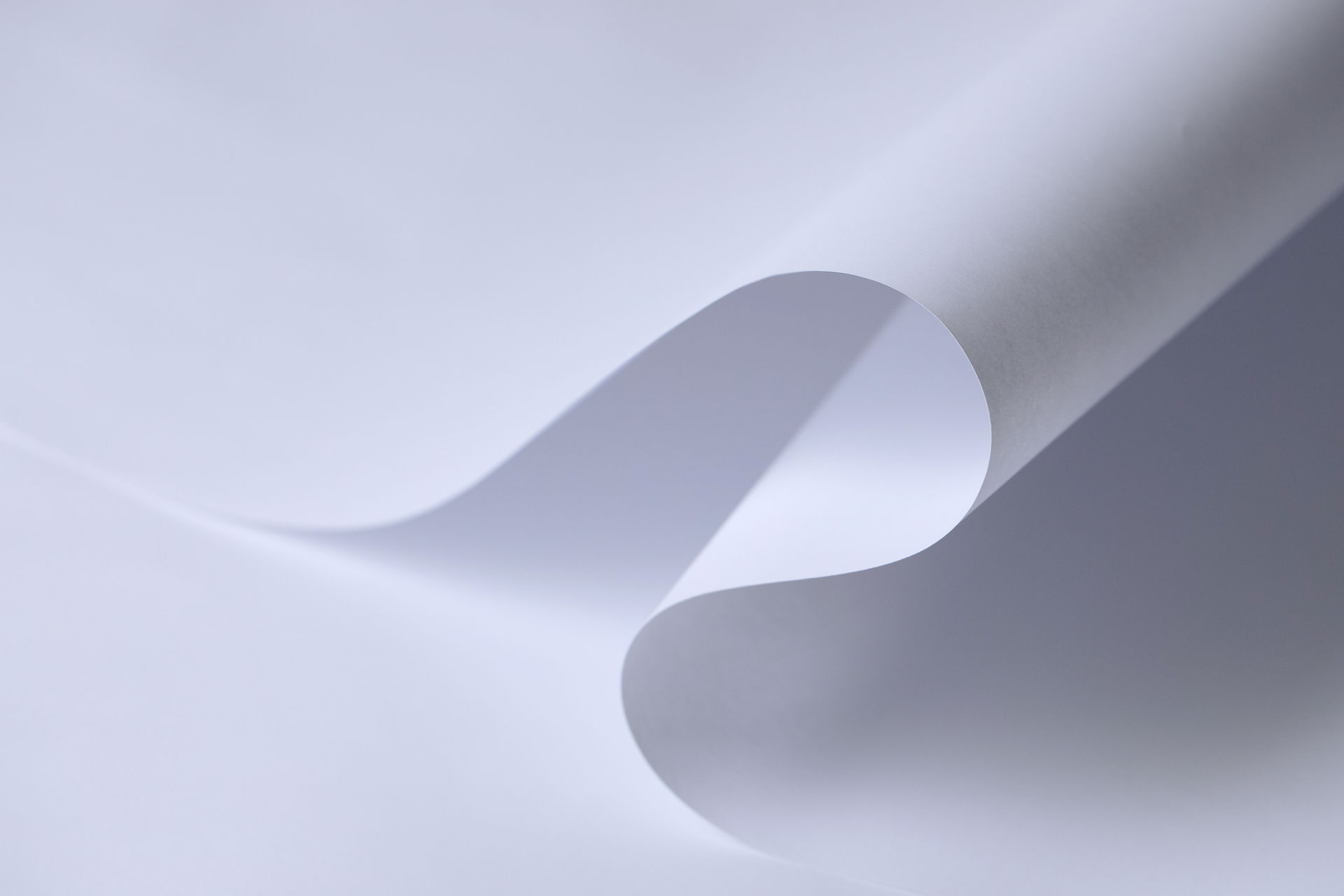
日々の泡
演劇小論
下手な役者
下手な役者に限って、本を責めたり、他人を責める。自己防衛の為に、自分より手下な役者に君臨し、楽屋裏話をする。もっと馬鹿な役者は、こう言う人の話に追従賛同して自分を見失う。
下手な役者等に限って予定調和を嫌いだと言っておきながら、一番予定調和の芝居をする。つまり、台詞に心を入れずに、ただ流した芝居をする。
さて上手い役者は、自分を責める。そして自己弁護を行わない。予定調和などと言う言葉を知らないから、今生まれた言葉のように台詞の役柄になり、自然な演技をして、台詞に命をあたえる。人を信じるから、人を説教しない。人を信じるから、徒党を組まない。どうぞ、諸君!
染まらず、素直に、ワクワクを忘れず、いつも見てくれるお客様の為の役者として、つまり、奇跡の愛の使者として、いい演技を期待します。(2016年10月塾生へ)
劇場へ、そして酔って、狂って、町に出よう!
30歳で刑場に散った吉田松陰の生涯を描いた小説や評伝は沢山ありますが、私が心を動かされたのは「天皇の世紀」(全12巻)と言う大仏次郎の幕末史を読んでの事でした。この本は、恐らく人々から顧みられること少なくやがて歴史に埋没されてゆくかもしれませんが、恐らく近代日本の生んだ稀有の記念碑的重要な歴史書だと私は信じています。この書物で扱われる松陰は、幕末の夜明け、その密航顛末と小伝馬町の最後のシーンですが、この大作の中に蠢く志士や幕府人、異国人の言動の青春像を根底に、私なりの想像の世界を創りだしたのが今回の芝居です。
「諸君、狂いたまへ!」と松陰は絶叫しました。何故に?
この言葉は私の中で「つねに酔っていなければならぬ。万事がそこにあり、これこそ唯一の問題だ。君の骨を砕き、君を地面に押し曲げる時の重荷を感じないためには、絶えず酔っていなければならない」と言うボードレールの詩から、やがて寺山修司の「書を捨てよ街に出よう」と言う若者への問いかけの言葉へと円環を描いて、何時も私の心の中で劇化され続けてきました。
今回、この芝居で出会った若い役者諸君が、どうかこの舞台体験で狂い始め、やがて日本の演劇界に酔って出る日を期待しているのです。芝居とは狂気の世界を日常化してみせる道化です。道化が伝説を作る。松陰は生きた道化であり続けました。 (2016年10月5日)
古い演出家は、自分にそぐわない役者を排除する。
自分の演出を自画自賛する。それが、あたかも新しい事かのように誤解しているからだ。その見分けがつかない役者は、自分も新しいかのように、古臭い演出に溺れてしまう。こうした、どつぼにはまった同士の教団芝居など反吐がでる。新転落だ。
経験という量を他人の考えの及ばない質に創り変える潜在能力、それをスターの持つオーラというのであろう。
芝居とは虚構である。
虚構が真実(リアル)を映す鏡となる世界である。自分を虚構の世界に追い込めない者は役者とは言えまい。まず正確な台詞の再現を成し、その上で自然体の演技とは、虚構の極致の地平線に現れるものだと思う。
自然の、恐ろしいほど見事な「花の姿」を演じるには、どうしても人は化けねばなるまい。その変化の中にこそ華は咲き、整然とした自然が映し出されるだろう・・・そこでは遂に、役者とは狂気の世界を日常化してみせる道化者であらねばならない。
(大輪塾公演「上海奇兵隊」ノートより)
「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に、成功なし。諸君!狂いたまえ!それだけのことでしょう」(大輪塾公演「漂流者」ノートより)
「思想を維持する精神は、狂気でなければならない」(吉田松蔭)
然り。今宵、老いて尚、諾!
演劇は面白い生き物だ。
観客にとって物理的空間が、一人の役者の登場で心理的空間に変わる瞬間は生きてる彫刻の様だ。
さて、演出家は鑿をどう使うかだ。舞台(架空)に脚本(仮構)を掛け算して、虚構の物語が今まさに眼前で現実に起きてるようなリアリティに生まれ変わるエンターテイメント魔術。
だが役者自身の生の生活実態が、虚構に侵入すると舞台は、たちまち台無しになる。下手な演出家と下手な役者は舞台をただの遊園地にしてしまう。演劇と言う言の乗り物に乗って本人たちだけが酔いしれて楽しんでるだけで、観客は欠伸してしまう。
さて、最近見たメジャーからマイナーの芝居は殆どが、当人達だけが喜んでいるお子様達によるお化けのお遊戯大会だったナ。
「今日誰々君がハムレットって役演じてたよ!」と言う話は良く聞くが「今日ハムレットと言う人間とそんな場所に会って来たよ!」と言うような話はなかなか聞かないものだ。役者の名前が前に出て、物語の影は薄くなるばかり。
「最近の役者は本が読めない」と久世光彦さんが言ったが、役者に限らず演出家にも言葉が読めない人間が増えた今日、脚本の内容から観客が共感とか感動を受ける作品に出会うのは容易な事ではない。
映画や芝居見て何言いたいんだろうウン〜と頭を悩ましたくもないこの歳になると、作品の好き嫌いも必然的に限られてくる。僕には現代のアバンギャルド芝居や最新の映像技術を取り入れて得意になっているイベント風芝居などはまったく古い趣向にしか見えず、そこには演劇のなんの新しさも感じず、やはり古典の革新的物語性、言語の見事な重厚作品を演出家が役者の演技に託した舞台に、やはり古くならない新鮮味を覚える。
まして下手な役者が集められ、したがって幼稚な脚本演出家を見極められずにやっている雨後の竹の子のようなSFチック作品、学園物などのお子様ランチ芝居はもう見飽きた。
まあ、かくのごとき混沌が、何かを生むんだろうが、プロにしろアマチュアにしろ演劇プロデューサーも質より量を求められる時代に果たして新しい言語表現の演劇は生まれるのだろうか?
稽古中
まだ演出家の理想と役者の演技の現実に隔たりがある。
これで充分だと決めてしまえば、それなりに今の状況は許される高得点と思えても、頭の中に理想が見えるだけに、尚そこに一歩でも近づこうと、役者にダメ出しして、失望感を与え、尚の努力を強いてしまう。
稽古とは両者の精神の緊張を計りながら、平衡を失わないように進む綱渡りのようなもの。失えば、理想も現実もゼロになってしまう危険な場所なのだ。
そして本番とは最早、充足した稽古の先にあるオマケなのだ。
演劇における役者のオリジナリティとは役者が「自分の内部の感情の表現」をするのではなく「他人の内部の感情の表現」をする事にある。
役者ほど厄介な生き物はない。
役者は脚本を自分なりの解釈で演じたがる。脚本の本質を、自分なりのものに変容するのが役者たる自分の真髄であり、それでこそが名優の技であるとおもいたがる。これは舞台を多く経験してきた役者に限って陥る弊害である。
この意識家ほど危険ななものはない。
例えば、素人は素直に脚本を読んで、その個々のキャラクターにイメージする素直な印象をキャラクターっとして作ろうと思うものだが、上手いと言われる役者に限って、そのイメージを変容し、この作意こそが、実は芝居を臭い物にしてしまうと言うことに気づかない、それは往々にして「渋い」演技をしたいなどと思ういやらしい欲望が実は精神に横たわっているからだろう。
改めて、ジュリエッタ・マシーナ
昨夜テレビでフェリーニの「道」を久々に見た。何回目だろう?
そして、やはり自分の創作の原点に深く影響を与えてくれた生涯の名作だと言うことをつくづく想った。
あらゆる人間の心に潜む美しくも醜い感情と思想が、サーカス、道化、流浪と言う舞台を背景に、一人の女優の演じる瞬時の仕草、表情自体が物語となり、それが筋となって紡ぎ出されて行く。
役者の至芸とは、まさにここに尽きる。
もし自分を役者と呼ぶ者は、願わくは謙虚に、この女優の演技を何度も何度も見て、打ちのめされる程に、その質を 自分と比べ、学んで欲しいものだ。
