(三)ポスター屋のギャラキツネ
翌日、居酒屋「ロレットット」の主人で、今回の劇団作りにもっとも熱をあげてしまったキジ親父が、さっそく山一番のポスター作り名人と噂されるキツネの所に出かけて行きました。
このキツネ、実はその昔、下淵沢に住んでいて、売れないポスターの絵を描いていたのです。キジ親父はそんなキツネが、木枯しの吹く下淵沢を、あっちウロウロ、こっちウルル、間違いだらけのギャラ刷りをもって紙屑のように走りまわっているころから面 倒を見てあげていたのです。杏子酒をただで飲ませてあげたり、里芋の煮っころがしを食べさせたりして、応援してあげていました。それが、いつの頃からか、山犬のケンタ君の紹介で西土ノ森劇団の仕事をしてからというものは、トントン拍子、今ではトカイ山でもおおいそがしのデザイナーになっておりました。
そんな訳で、キジ親父は近頃めっきり姿をあらわさないこのキツネに、今度の公演のポスターをたのめば何とかしてくれると思ったのであります。
キツネの事務所は、ぶなや樺の林が良く整備された麻の実の丘にありました。
「おお、おお、あいつも立派になったもんだ。」
キジ親父は、すっかり磨きをかけられた桜の階段をのぼりながら、枝にかけてある数々の白樺の賞状を見て言いました。それから、さらに階段をのぼると、受付のようなものがあり、一匹の牝キツネがすました顔で、真っ赤なグミの実液を爪に塗っていました。
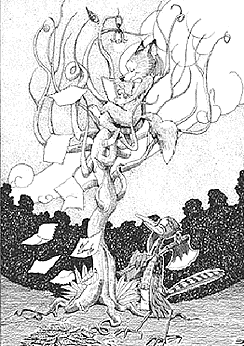
「ハーイ、あのね、ギャラキツネはいるかね。」
「ギャ・ラ・キ・ツ・ネ?」
そう言うと牝キツネは、キョトンとした顔で目の前に現れたキジ親父を見つめました。キジ親父は頭にいつものようにトレードマークのバンダナを巻き、髭は仙人のように伸ばしていましたから、これを見た牝キツネはすっかり目を丸くして、あまり頭の良くない異国かぶれの女の人がやるように指を一本立てますと、チィ、チィ、チ、とそれを左右にふりながら言いました。
「ああ、出前を下げに来たのネ、それなら裏口にまわってちょうだい。」
「ヒュヒュウ、お嬢ちゃん、おもしろいね。キジはいつも表を使い、キツネのお稲荷さんは裏を使うと味がしみてうまいなんちゃってから。イエィー!」とか何とか意味のないことを言いますと、キジ親父は少しも動じないばかりか、床の上で
一回転しました。この親父のはなった、最後の「イエィー!」は口ぐせで、もっと気分が乗ってくるとそれは「ヒッエィー!」になるのです。
この時、ポスター屋のキツネは、この声を悪い予感をもって部屋の中から聞いていましたが、ちょっとばかりドアーから顔をのぞかせると、「何だ、そうぞうしい。」と牝キツネを怒鳴りました。
「やあ、ギャラ公、いるんならいると早く言いなよ。何だ水くさい。元気かね、僕よ、僕。ヒッエィー!」
キツネは、やはり一瞬ドッキリし、もうすっかり身体中の毛をピンとさか立ててしまいましたが、
「ああ、エエート、どなたかは存じ上げませんが、入り口で騒がれては他のお客様の迷惑になりますので、まあ、とにかくひとまずは中にお入り下さい。」
こう言うとキジ親父を、部屋の中にさっさと入れてしまいました。 「おお、こんないい部屋に入って、ずいぶんと気取ってやがらぁ、なあ、このギャラ公が。」
親父さんは立派な苔のソファーに座ると、うれしくて仕方ないと言った調子でポンポンはねました。苔総張りの高級椅子の様子を心配げに見ながら、
「その、ギャラ公と言うのはひとつかんべん願えませんかね。こう言う私めには、今ではミスタープリント・オブ・フォックスと呼ばれる有名な名前がございましてな。コッホン。」と、ギャラキツネは言いました。
「へん、から咳なんからしちゃって。そんな舌をかみそうな名前より、さぞかしやお前さんなんぞミス・プリント・デ・ギャラ公てな所だろう。なあ、ギャラ公、ギャラ公が悪けりゃ冬空の下のからっ風野郎。」
「もうもう、何でもいいですよ。親父さんにかかったらこの始末だ。それで、今日は又どんな御用ですか。」
ギャラキツネは少しプリプリして聞きました。
「おお、そうだ、そうだ。今日はちゃんとした仕事のことで無理なお願いに来たのだから、ちゃんと聞いてもらわなくて。」
こうキジ親父が言いますと、ギャラキツネはコホンとひとつ咳ばらいをしながら、さもずるかしそうな目をむけました。
「無理なお願いですって。ウーン、そうなると言っておかなくてはなりませんが、私は、今、大変、忙しいですし、仕事は、一流ですから、ドングリの方もはります。先日だって蛇の目傘演芸クラブが、一年先の公演ポスターを、頼みに来ましたが、話にならないので断ろうって思ったくらいですよ。」
「あの売れてる動物タレントを一杯置いている、蛇の目傘演芸クラブがだって。」
「そうです。あそこには、今、売れに売れてるサギの子トリオがいますがね。どうもあの手の、歌も芝居も出来ない子供だましに人気があるのも困ったものですな。知ってますか、今、一番科学的に新しい蓮の葉レコードが、なぁーんと全国の栗の木亭放送局で百二週も一位 、もうこれは動物演芸界の新記録、売上枚数だって、五十兆万枚てんですから驚きます。蓮の葉がもう足りなくって困ってるって言うんですな。」
「ハスノハのレコードだって、僕、そんなの知らなかったな。」
キジ親父は普通でも開いていないような目をさらに線のように細めて、
「ウーン、この業界はやはり進んでいるな。それにしても今年は蓮根が中々手に入らないわけだ。」なんどと、ため息をもらしました。
「ああ、そうです。その売れっ子の蓮の葉レコードの表紙とポスターをですよ、コホン、この私が頼まれましてな、先方がどうあっても先生にここはひとつ何とかしていただきたい、それだけで売上枚数が百万は伸びますからと、あなた、目の前のここで床に頭をつかれて頼まれては、いやいや、私も断るわけにはいかないでしょう、そこまで言われてはと、コホン、いやいや僕も人がいい、つい引き受けてしまいましたがね。なにせ売れてるもんですから、いやいや、あんな子供だましのサギの唄がですよ。いやいや、コホン。」
ギャラキツネはそう言うと、胸のポケットから高価な松茸葉巻を取りだし、火をつけました。すると、
「風邪でもひいたのかい、あまり無理しちゃいけないよ。」 キジ親父はこう言うと、ギャラキツネの口から葉巻を取り上げ、さもうまそうにスパスパと吸い始めました。
「風邪を?誰がひいているんですか。」
「おまえさんだよ。」と、キジ親父がスパスパ煙を吐き出しました。
「コホホホン、おお、煙い、それで、どうして僕が。」とギャラキツネが又、聞きました。
「ほらほら、さっきから、しきりと話の間にそのコホン、コホンをやってるものだから、それが気になって何を話しているのかさーぱっり判らなかったな。そうそう、それにそんな時、煙草を吸ってはいけないよ。身体には気をつけたほうがいいよ。いつポックリいくかも知れないからね。今は、働き盛りの狐が死ぬ 時代だよ。」
「大きなお世話です。ぼくは風邪なんかひいてませんよ。ウウン、もうそれで話というのは。」ギャラキツネは、もうすっかり疲れた様子で聞きました。
「そうだ、そうだ。」 こう言うとキシ親父は、昨夜決った劇団の一件とそのポスターをギャラキツネに安く作ってはもらえないだろかと相談をもちかけました。これを聞くとギャラキツネはもう、腹を抱えて笑いころげ、最後には机の上で四回も宙返りをしました。
「何がそんなにおかしい。」今度はキジ親父の方がむっとしてギャラキツネを睨みました。
「何がおかしいって、あの連中が芝居をだって、コホホホッホ、あ、おかしい。そしてそのポスターをこの僕に頼みたいですって。コホホホッホ、ああ、愉快、不愉快。」
「わしたちがちょっと遊びで劇団を作ろうと言うのだよ。それのどこがいけないかい。 それに鷲のギンジロさんも、山犬のケンタ君も専門家なのにちゃんと手伝ってくれるのだぞ。」
「古いんですよ、古い。ギンジロも山ケンも。だから彼らは売れなくなっちゃたんです。あいつらがやってた時代の芝居や唄は、もうこの動物世界では古いんです。今はこうですよ。今や落ちてる人間も起こしてやる勢いの作詞家アキモタヌキ大先生が作った曲をお聞きなさい。」

そこでギャラキツネは「おい!」といって隣の部屋に声をかけると、一本のワラビ巻きテープをもってこさせましたが、持ってきたのは眼鏡をかけた亀で、それを背中で運ぶのに十分間もかかりました。きっとこの事務所の経理をまかされていたのだと思います。
ギャラキツネはワラビ巻きテープを最新式の竹の子プレイヤーにかけました。流れてきた音楽は、北極海峡のオットセイ達が作ったといわれるレゲゲッゲリズムというものをバックにしたサギの子トリオの唄です。
キジ親父はこのレゲゲッゲリズムがもう死ぬほど好きで、オットセイ達が教祖とあおいでいるボンド・デ・マリの柏の葉レコードを何枚ももっていました。もう、それはしょっちゅう「ロレットット」でかけています。ギャラキツネはそのことをすっかり忘れていました。「しまった!」とギャラキツネが思った時はもうおそかったのです。
「ヒィエィー!」
キジ親父はひと鳴きしたかと思うと、もうあたりかまわず踊りはじめていました。
スッチャチャ スッチャ スッチャチャ スッチャ イッエー! (これはキジ親父の奇声です。)
スッチャチャ スッチャ スッチャチャ スッチャ ヒィエィー!(これもキジ親父の奇声です。)
ぼくたち、ガラスの靴はいた
サギの君を今夜もまっている。
風になびいた、その羽根の
香りが夏の思い出さ
イッエー(もう、おわかりですね。これも・・)
スッチャチャ スッチャ スッチャチャ スッチャ
これ以上ここに書くのもしのびないほどのアキモタヌキ先生の詞と、餌を欲しがるサギ雛のように調子はずれの唄声が流れていましたが、キジ親父はそんなことおかまいなし、ただ奇声をはっしながらリズムにあわせて踊りつづけていました。
ガシャ、(テープが止められた音です。)
「ちょっと、ちょっと親父さん。もう終わりましたよ。」
それでも踊りつづけているキジ親父にギャラキツネが言いました。
「ちっともわかっちゃいませんね。今はそんな風な、月見草音頭みたいには踊らないんですよ。編曲のリズムだってレゲゲッゲに似ているけど、東南アジア的で、どこか違うんですよ。」
「もっとつづけろ、イッエイ!えっ、どこが違うの?」
踊りをやめたキジ親父がたずねます。
「ほら、ここのところが」といってギャラキツネは又テープを回してしまいました。
「ヒィエイイー!」
するとまた、さっきと同じことがおこりました。
ギャラキツネは話にならないとプリプリ怒って、今度は自分でテープを隣の部屋にしまいにいきました。三十秒しかかかりませんでした。そして戻ってくると時計を見ました。
「わあ、大変だ。こんなくだらないことで三時間も大切な時間をすごしてしまった。親父さん、とにかくこの仕事はやれませんから、今日はもう帰ってください。」
