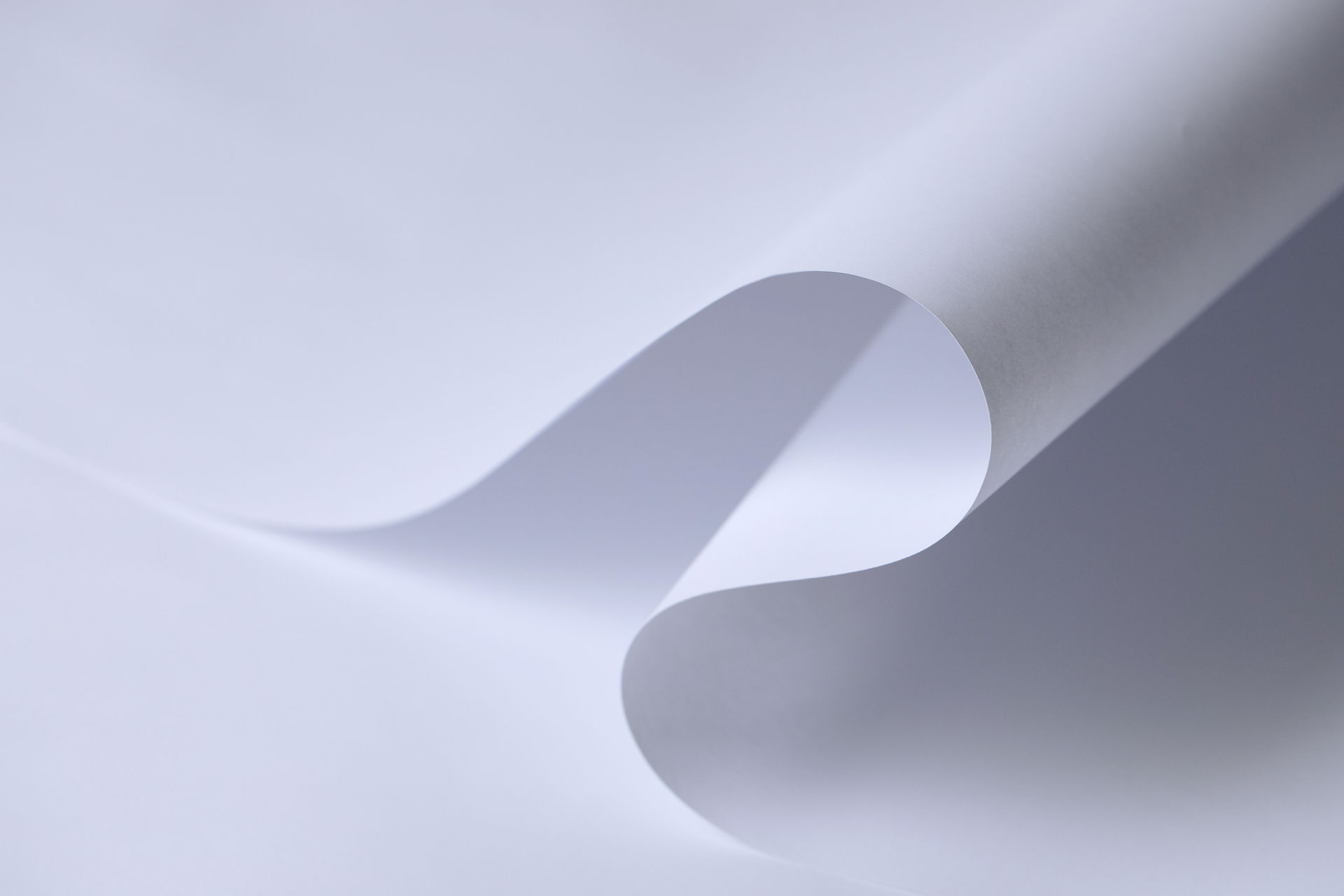
日々の泡
著名人・人々
喜びと、悲しみと 永六輔
今日は木の実ナナさんの誕生日祝いを夕暮れの東京湾クルージングで行った。益々元気なナナさんに英気を貰って来た。
でも、心の奥には悲しみがある。
ナナさんを可愛がってくれた師匠の永六輔さんが亡くなったからだ。
僕は駆け出しのマネージャー時代にナナさんを通じてこの奇人と出逢った。劇団四季からの出演依頼を僕はお断りして、小沢昭一さんが立ち上げた劇団芸能座第一回公演「清水次郎長伝・伝」に参加する事を選択。ナナさんは次郎長の妻お蝶役で出た。この芝居の脚本出演が永さんで、僕は初めて永さん達と全国を一年ドサ廻りした。山口崇、加藤武、山谷初男さん、まだ無名の役者栗山民也もいた。1975年の事だ。
「おまえさん」の音楽ディレクターをした時、一番にテスト盤をお届けしたら「さすが阿久悠だね〜、このタイトルはイイね」と作詞家永さんはちょっと嫉妬ぽく褒めてくださった。
今日あたりは京都は宵山祭りである。永さんが高石ともやさん達と始めた円山公園での「宵々山コンサート。そこにも呼ばれてナナさんと行った。懐かしい思い出の日々だ。
さて、もう一つ。
ザ・ピーナツの妹伊藤ユミさんが亡くなっていたと言うニュースも届いた。
渡辺プロ時代、それからジュリー沢田研二とプロダクションを作った時代、お宅にお邪魔し手料理を頂いた事など、忘れられない。
まさに、人生はLA VIE S'EN VAの感、深し。
(2016年7月11日)
歌謡射撃手の眼光・平岡正明
今私の手元には平岡正明著「歌謡曲見えたつ」(1982年発行)という一風変わったタイトルの本がある。この筆者に関する追悼特集号を出すから貴方も何か感想を書け、と言われて編集者から送られて来たものである。
歌謡曲が見えたなどとは、いかにもタイトルをモジっているように思えるが、実は本書の内容は著者自らが述べているように、「筆者初の歌謡曲各論集」で、1980年から二年にわたり「プロダクション、レコード会社、あるいは歌手本人からの売り込みも抗議もうけつけず、こちらもインタヴューせず、クールにかつ一方的に」ライフル狙撃したという趣旨で雑誌に連載した音楽コラムと、時には歌謡曲に最接近して手榴弾を投げ、白兵戦したという中編論文を併せた歌謡評論集である。そして読後、私は思った。まさにこの本には闘う射撃手の立場を貫き通した者だけがなせる独断的な、「清濁併せ飲んだ」壮絶な情熱的歌謡曲論が散りばめられている、と。思うに、この本で筆者は確かに歌が見えたのであり、流行歌が聴こえたのではなかった。音楽評論の為に毎年年間千曲にも及ぶ音楽に直に触れ、聞くという労働作業した者の「耳」には、歌謡という生き物の姿が、或はそこを通して分析できた歌謡曲世界の有り様が「目」で見るごとくにまざまざと彼の眼前に立ち現れたのである。そこで思わず、叫んでしまった、俺には「歌謡曲が見えた!」と。こうした感想を私に喚起させるに充分な筆者の文章、音の視覚化、文字化された肉体言語が本書には、時代を超えた生き物のように蠢いているのである。
私ごとになるが、氏がこのような歌謡論を勢力的に書き進めていた1980年代初頭というと、それは音楽業界を渡り歩いて来た自分が「桃色吐息」の佐藤隆と独立音楽プロを作り、さらにはこの本にも触れられている「沢田研二はどうストリップしたか」(82年)というその彼と再会し(それ以前、私は沢田研二と井上尭之バンドのマネージャだった時期がある)やがて彼と仲間と「CO-COLO」という独立プロを立ち上げていった時期でもあった。まさにそれは平岡氏の文章を借りれば「脳天気で外側に倒錯」してゆく佳曲を歌い続けて来たスタージュリーが初めて「内省的で、自虐的で、苦しそうに」今までに見せたことのない顔つきでヒット曲「ストリッパー」を歌い、新たな進路を模索し始めた時期と重なるのである。
実はこの頃、私には、この世で好きになれないタイプの人種がふたつあった。一つは浮かれ手拍子で私たちに近づいて来る芸能レポーターと称する、狂犬病的であるがゆえに反省能力の欠如したマスコミ人間、もう一つはその芸能界の音楽や歌手に関する蘊蓄をチトンシャンと並べ揃え、いわゆる「通の顔」をした芸能音楽評論家と称する、これもまた芸能レポーターと精神的共存関係にいるかに思えた人たちだった。芸能世界にどっぷりと生きて来たお前が何を言うかと非難されそうだが、その芸能界に身を置いてきた故に自分の中に芸能界マスコミ嫌いの精神は確実に内在発芽していたと思う。そして沢田研二と仲間たちとより自由なロックへ、大人の音楽へ、稚拙なレポーターや評論家に紛動されないオーディエンスと直接握手すべく、進むべきそのエンターテナーな音楽世界志向を模索していたのである。このような時期、私は私の嫌厭するレポーターや芸能音楽評論家群の中に「勝手に引き金を引いて、自分の弾丸を音楽業界に撃ち込み続ける」一匹狼的評論家平岡正明という人間のいることを知らなかった。日本の音楽批評はまだ成熟していない、歌謡という生き物たちを扱うのだから、こちらも真剣に肉体で闘え、そして世の「音楽評論家は俺に続け!」と叫んでいる人のあることを知らなかった。
そんな私が当の平岡正明氏と知人の紹介を通じて直接お会いしたことが一度だけある。「COCOLOと別れて数年後の、ある冬の日のことであった。私は氏に既に「歌謡曲見えたつ」の著作のあることも知らなかったし、その日どのような話を氏が私にしてくれたのかも良く覚えていない。ただその変わりに、私は私なりにある「感想」を平岡氏に話したのを覚えている。それは日本の芸能音楽にも通じる「半島の旋律」と言った私論で何故か平岡氏には聞いておいて欲しいと思った。実は世界中の半島の音楽、いわば大陸を背にした海辺の先端に位置する場所に誕生した音楽、そこにはメロディー、声質はもとよりそこに通底するある同質な悲しみにも似た感性が一貫して流れている、という私のジプシー的放浪歌謡に対する長年に渡る持論でもあった。氏は笑っていたが、その目を細めて聞いて下さった。書けよ!それは面白いからと示唆する、真剣な眼差しであったことも記憶する。だが、私の筆はその後中断したまま、時が流れてしまった。
さて現在、私はBOROという歌手の三十周年を記念するアルバムの編纂作業に関わっている。そんな訳で我田引水と言われてしまうかも知れないが今回の氏の「歌謡曲」を読み進めるうちに、秀逸と思える音楽コラムに出会った。それはまさにボロの80年発表の新譜「走る階級」を論じた「ロックンロール怨み節」という文章である。当時ボロはこの曲で自分は走る階級で、親父も自転車にアルミの弁当箱を載せて町工場に走る階級だが、俺の想うあの娘も走る階級で、でもあの娘は庭の芝生でジョギングし、ジャガーで優雅に走る階級なんだと、歌った。さてこのシチユエーションを受けて平岡氏はまず「階級」などという歌謡に新鮮な言葉を使ったボロを讃え、さらに裁断する。即ち「若松映画なら走る階級のそのような女を犯せ、と発想する所をボロはじっと上目づかいに見る。矢沢永吉のようにだから俺はビッグになって見返すとは言わず、アナーキーのようにやっちまったあとでスローガンが追いかけて来るような若さの暴走も無いし、パンタのような観念のラジカリズムもない」とパッサリ切り捨てる。ではボロとは何か?それは百姓の卵の殻をまだつけた日本労働階級の閉鎖性であり、その階級に固執するロッカーなのだ。そして敵階級とは実は自分の中にある優柔不断さなのだという事を一番気づいている、その傷つきやすい階級の心の怨み節を歌うボロを俺は支持するよ、と平岡氏は論じたのである。私は時代がまだ貧乏人と病人で溢れ、その味方であろうと決めたボロ、そして庶民に対し変わらぬ同苦の姿勢を保ちながら今日まで生きている彼を見て来たが、そんなボロの魂音楽に対する共鳴をわずかな紙面の中に愛情を以て綴った平岡氏の情熱的狙撃—視線のあったことに今更ながら感服した。
そんなボロがあの当時、歌手沢田研二に提供した名曲『優しく愛して』をもし平岡氏が聞いていたなら、氏が同じ本の中で論じたこの二人の出会いにどのような感想の弾丸を浴びせてくれただろうかと、そのことにも想いを馳せるのである。私には芸能界の中にも厳とした階級ステージがあり、ボロとジュリーとは一見非なるものながら、そこに通底するある労働者同士の共鳴感が、一幅の「濁り絵」として歌謡界に提出された作品だと思っている。だが、このジョイントはミスマッチだったという批判もあったことを記しておこう。
編曲家大村雅郎
昨夜、ある本の企画で、46歳で夭折した天才編曲家大村雅朗君に関するインタビューを受けた。
忽ち遠い昔が思い出された。出逢った頃の僕たちは若かった。
当時32歳の音楽デュレクターだった自分は5歳年下のまだ新人の(と言ってもこの時八神純子の「みずいろの雨」を手がけていた)彼を起用して木之内みどり「一匹狼〜ローンウルフ」(大野克夫曲 東海林良詞)、石川ひとみ「くるみ割り人形」(馬飼野康二曲 三浦徳子詞)、根津甚八「ピエロ」(中島みゆき曲詞)、そして永井龍雲や彼らのアルバムの編曲を立て続けに依頼したものだ。
その後1984年沢田研二君に曲を依頼し、リタ・クーリッジでロスレコーディングした「美しき女」のカップリングには大村君の名曲「Sweet memorise 」を収録し、そのメロディの質の高さを外人から絶賛され、日本人として誇らしかった。
さて、今回の取材で大村君と会った当時の写真をと頼まれ、探したら、このようなファンクラブ掲載の写真記事が出て来た。初めてパリへ行き、カルチェラタンのカフェで撮ったものだ。流石にみどりも僕も若い。このパリから帰国後、すぐに作ったのが「一匹狼」だった。
ヨーロッパ志向の僕はその後大村君とは、良くクラシックのレコードをお互いの家で聴き合い、彼に随分貸したものだが、それ以来会わないまま時が過ぎ、彼は逝ってしまった。大沢誉志幸、松田聖子などへのアレンジを多く残し、急ぎ足に・・。
錫の酒器とジュリー
昨夜、錫の酒器特集をたまたまテレビで放映しているのを見て、棚をゴソゴソ、最近使ってなかった器を取り出した。
沢田研二のデヴュー20周年記念パティーのお土産用に江戸切子の小グラスとは別に特注して作らせた錫のタンブラーだ。裏に「錫半」と銘があるが、実は1714年の江戸時代、日本で最初にこうした錫器製造を始めたのがこの大阪の老舗「錫半」だった。だが、次第に錫器業界に翳りが見え、職人も減り、ついに20年程前にこの伝統工芸店は廃業に至った。
だが錫はその特質上、錆びず、保菌力があり、水やビールを美味くし、日本酒を見違える味に変える素晴らしい器だ。使えば味も出る。また、愛用しよう。
さて、20年前に「もっと走れ!ジュリー」と祝った彼も今年でデヴュー50周年目を迎えた。エンターテイメントの名器と言えようか。
(2017年7月19日)
Boro のアルバム「shout 」
シャウト【shout】とは?叫ぶ事、とある。
人は叫びたい時がある、叫びたい事がある、叫びたい場所がある。どんな時、どんな事を、どんな場所で?
問題は、それを何処に向かって叫ぶのか?自分にか、貴方にか、君にか!星にか、花にか、宇宙にか、希望に向かってか?自分が信じるものにか!
友人のBoro が「shout」というアルバムを出した。
歌手ボロのシャウトだ!この冬、彼が愛する歌たちを、彼がギター、一本、一人スタジオで!
シャウトとは何度も繰り返せない、その時の一瞬の心情の発露である。ボロはこのCDを一発どりで録音したという。とすればそこには、その時の、その場の、一瞬のボロの感情思想の定着が刻まれてなければならない。果たして僕は、聴いて、一瞬ボロが目の前にいるかのような錯覚を覚えた。何という無秩序な衒(てら)いのない歌唱、節まわし、強弱な声量が生で聴いているように流れ出して来たのだ。そして、彼は自分に向かって歌っている!彼の心の中にある、人への優しい思いやりや声援という魂に向かって、僕は今叫ぶよ、叫び続けるよと歌っている。
人への想いを、自分に向かって叫ぶ!これが孤独なアーチストからの人間連帯への贈り物なのだ。
一曲一曲については書かない。聴く人が音と対話して欲しい。「ネグレスコ」から始まって「ランナーの孤独」までの言葉の数々が、ボロによって立体化され、劇化され、そこに提示されている。
そして、
「あきらめの停車場も過ぎて、街の灯りが見える。苦しみに汚れない勝利など聞いたことが無い。立ち上がれ、立ち上がれ!」
彼はそう叫びたい、そう叫けび叫んだ、そしてこれからも、そう叫び続けるだろう!
昨日は世田谷ボロ市を覗いた後、渋谷へ永井龍雲デヴュー40周年記念コンサートに招かれて出向いた。彼のデヴューのレコーディングディレクターが自分だった。
当時ポニーキャニオンの中にNAVE というアイドルのレーベルがあり、岡田奈々、岸本加代子などがいたが、渡辺プロを退社した自分はそこに就職をして木之内みどの担当となって「横浜いれぶん」などのヒットを出していた。そこへタイガースやキャロルのプロデューサーだった僕の師中井國二から九州にいい新人がいるからやれと紹介されたのが龍雲だった。キャニオンには新人の中島みゆきや松山千春、谷山浩子などのフォーク班があったが、そんな訳で龍雲は僕の所属するアイドルレーベルデビューとなり、以後、中井さん、大野克夫さん、井上堯之さん達で作った音楽事務所「water」と九州のクスミュージック岡本君とタッグを組んで龍雲の様々な活動を開始したものだ。今は亡き編曲者大村雅朗君が駆け出しだったが採用し、グアム島の大野さんのスタジオでレコーディングしたり、やはり自分が担当だった根津甚八に曲を提供したり、思い出深く懐かし時代だった。
あれから40年!
彼の声量は変わらず、とても風格のある男に育っていた。日本のフォークを育てた懐かし面々とも久しぶりに飲めた一日だった。
原田芳雄さん七回忌命日
最初に東北沢の原田宅へ連れて行ってくれたのは内田裕也さんだった。自分の住まいと原田宅は小田急線を挟んですぐ近所だったので場所は知っていた。細かい事は省くが、その日原宿で裕也さんは僕を家来の様に従えお土産のジーンズを探し求め、僕は当時勤めていたレコード会社が出した志ん生の落語全集CDを持参していた。原田さんが、落語が大好きと裕也さんから聞かされていたからだが、余計な口を聞くなよと言われていたのでお邪魔してもジッと黙って二人の会話を聞いていた。漸く時を得て志ん生を差し出すと、原田さんは破顔狂喜、話に花が咲き、裕也さんはムッと嫉妬したようだった。
以来、仕事はご一緒した事はないが、沢田研二のプロデュース時代などに出会うと必ず「ヨー!」と迎えてくれた。売れない人間椅子の音響担当の女性が原田さんのライブでも一緒だったので彼女のささやかな結婚披露宴では人間椅子の演奏でブルースを歌ってくれたりもした。さらに僕が手がけた無名の天才ボーカリスト酒匂みゆきの歌を愛してくれた。
最後にお会いしたのは、病で入院していたと聞いていたある日、小田急線の踏み切りだった。ふと見ると原田さんが電車の通過を待ってぽつねんと立っている。
やはり「ヨー!」「お久しぶりでございます、お加減は?」の挨拶、そして「すっかり弱くなるね〜」と言うような言葉を二言三言。踏み切りを一緒に渡ると、それから右と左に別れたのが今生のグッドバイだった。決して深い付き合いではなかったが、近所馴染みというか、会えば笑顔で包んでくれる、心に温かみをくれる大人な人だった。
去って、七年。原田さんの亡くなった歳に自分もなった。
RIP リンゼイケンプ
僕の舞台演出に多大な影響を与えてくれた偉大な演出家にして舞踏家R・ケンプが亡くなったという報が入り悲しみに打たれている。
思い出せばキリがないが・・。
ある日彼の舞台「フラワー真夏の夜の夢」を見て衝撃を受けた僕は当時自分がプロデュースしていた沢田研二の舞台演出を頼むのは彼以外にないと決め来日中の彼を訪ねた。ケンプはジギー・スターダストなどデヴィト・ボーイやケイト・ブッシュに多大な影響を与えていたが当時ジュリーと内田裕也さん以外はこの企画に乗ってくれる者は少なく、結局話は流れてしまった。彼との会食の席、日本の矢立をプレゼントするとサラサラと僕の似顔絵を何枚も描いてくれたのが手元にある。
その後「君は私のカンパニーに来て勉強しなさい」とフランスに誘われたが、それも叶わず、後年僕が童話作家として食べて行こうと自費出版した童話集「夜出る魚達の船」には神戸公演の最中に表紙と挿絵をスケッチブックに描いて通訳の方から届けてくださった。
思い出は尽きない。
彼の作る不思議な舞台構成の色彩や光の世界、衣装の色、道化的美学などは今でも僕の心を強く掴む、いわば師匠であった。お礼申し上げます。合掌。
合掌 アズナブール
学生時代、最初に「イザベル」に出会った。狂おしく、悩ましく、セックス中の歌とはこういうものかと、ときめき衝撃だった。
それから社会に出て、僕の四畳半の生活はかぐや姫の「神田川」のようであったが、そこに出てくる恋人たちはきっとフランス文学を語り、アズナブール の「ラ・ボエーム」を愛してる者達に違いないと思っていた。「イザベル」の影響で生まれて初めて布施明の「そっとおやすみ」を制作した。
人生に嫌気がさすと、「世界の果てに」を繰り返し聞いた。あれはランボーの放浪の夢なのだと思いながら。
「Non je n'ai rien oublié」で大人の恋の痛みを知った。
思えば誰よりも、ずーと、彼の歌と、シャルル・デュモンの二人が僕の音楽人生の根底にあった。仕事ではロック関係が多かったが僕の個人的趣向は、音楽に関してはちっともアメリカや英国のロックミュージックなんかではなかった。シャンソン、シャンソンだった。アズナブール だった。
この動画を観よ!この手が僕の言うところの「 Act Singer」
合掌
東由多加「十月は黄昏の国」
今日、青春に胸躍らせたアルバムがふと見つかった。東京キッドブラザースの初期ミュージカル作品だ。
寺山修司と天井桟敷を立ち上げた東由多加は大学の一年先輩だったが、出会ったのは28歳ぐらいの頃だ。既に東京キッドで「ゴールデンバット」を作っていた彼がひょっと渡辺プロに現れて、ミュージカルを模索していると言ってきた。それから付き合いが始まった。
その頃の舞台がこの「十月は黄昏の国」だった。加川良、小椋佳さんの手になる劇中楽曲を坪田直子さんと団員たちが歌っているのだが、強烈な刺激を受け、擦り切れるほど聴いたものだ。柴田恭平はこれが舞台デビューだった。音楽ディレクターはワーナーパイオニアの友人友久君だった。
こうして聴くと、蘇るな、青春が、酒が、激論が。
泥酔して殴り合ったりした東由多加は2000年、若くして黄昏の国へ旅立った。
沢田研二
文春からの取材申し込みが昨日あり、それを断った。自分の思う事をここに書いてみる。
「黙って見てろよ」
50年以上、様々な荒波の中を絶えずトップで走って来た男の事を、たった1日の出来事を見聞して、知ったかぶってとやかく言う勿れ。専門家ぶるな、利用して何かを儲けようとするなよ。そう言う輩の君達はそんな長きに彼と荒波を共に付き合ってきたか!
彼の今回の反省には彼なりの深いものがあると思う。
彼は黙々と実生活を生き、燦然とスキャンダルチックに舞台で演じる事を自分の宿命として生きて来た男です。
だが星は曇った日には現れない。晴れた満天の夜に輝きを見せるものだ。彼はそれを知りながら、遂にそこに昇った。そして良く星が見えるようにと、その雲を払いのけようと努力するスタッフやファンにも囲まれて来た。
さて、では50年以上輝いて来た彼のこれから10年、その間に今流行りの新生星がどれだけ消えて行ってしまうことか。見上げてごらんなさい、彼と言う星はその時も悠然と輝き続けているに違いない。
ある時、僕はその時に売れてる歌手の歌をカバーするように勧めた。すると彼は「その人が10年後、まだ僕と一緒にトップを走っていれば歌う」と言った。果たしてその歌手は10年後には消えていた。僕はその間の彼の意地とも言える努力を見て、頭を下げた。
今度の件での、ファンに対する彼の反省の深さとは、その意地を実証する彼なりの明日へ向かう努力の約束事なのである。
老いて、なお、メインストリートのならず者!
彼はもう黙って、明日の夜空と言う舞台を見ているに違いないと僕は思う。自ずと結果を出すに違いない。スターの特質とは自らの責任で輝やかねばならないと言う宿命、使命を知っているものなのである。
それ故に、それ故に、諸君、稀代のスーパースターを、黙って見あげていろよ! (2018年10月)
追加
沢田研二には、ここ実に10年会っていない。 その彼のコンサートに昨日は久しぶりに行く予定にしていた。楽屋も覗いてみようかとも。なのに熱が出てドクター外出ストップ、この時に当たりこのインフルエンザは天の悪戯か配剤か。(今は熱も下がったが)
思い出すのは、やはり12年ほど昔、彼が私の還暦パティーに駆けつけてくれ、そこに居並ぶ嘗ての彼のプロデューサーやマネージャーや音楽スタッフだった人達を前にして私への祝辞をくれたのだが、その時「これからは自分一人でやって行きます」とまるで仲間への告別宣言にも似たような挨拶、その言葉が忘れられない。
あれから10年少しが過ぎ彼の変貌は目に触れ、聞き及んでいる。(笑)
ただ変わらぬ心の信念を直にこの目で見てみたかった。
行って幸いだったか、行かなくて幸いだったか、話題の大宮リベンジライブだったが、まあ病が治りゃ、また出会う日も、来るだろう。ジュリー、10年で80歳か、まだいけるぜ!
そんな事で、さて、今はただ寝ていよう。
「立ち止まるな、振り向くなあなた~」いろんな意味で、大好きな沢田楽曲だなぁ!
沢田研二「恋は邪魔もの」
彼にとって1974年は画期的な年となつた。
完全に井上バンドの音だけで制作された「恋は邪魔もの」(作詞安井かずみ・作曲加瀬邦彦)が発売されたのはその年の3月21日だった。実は70年代のヒット・シングルで、完全に井上尭之バンドの音だけで制作された彼のA面楽曲は実はそう多くはない。前年、彼をスターダムに乗せた「危険な二人」もロック仕立ての演奏であるが、演奏はスタジオミュージシャンであった。
だがこの74年という時期・・・井上バンドにはギターに速水清司が加わり、ドラムは原田祐臣から田中清司に、ベースはサリーこと岸辺修三、そしてキーボード大野克夫、井上バンド充実の音が出来上がった頃である。そしてこのシングルを契機に、沢田研二はその後の自分のスタンスを「井上尭之バンドのヴォーカリスト」に置いた感がある。タイガース、PYG、そしてソロデヴューと辿って来た彼の中には絶えずバンド願望があり、プロデューサー加瀬さんはそれを見越し、さらに当時のフルバンドやレコーディングミュージシャンによるレコードサウンドではなく、生のバンド演奏による新たなる日本のロックスター作りを目指したと思う。
こうして「恋は邪魔もの」はジャケットも井上堯之バンドの写真を散らばせ、バンド色を前面に押し出し、大野克夫中心の編曲によりリフを使ったロック調に仕上がった。「危険な二人」と「追憶」の大ヒットの狭間で世間の知るようなヒット曲とは決してならなかったが、彼の華々しい音楽史の中で「恋は邪魔もの」は画期的なシングルだったと思う。
この時、彼こと沢田研二26才、ボクは28才、私は彼のマネージャーになった。
当時渡辺プロダクションには歌謡曲班、ドラマ班、、ロックポップ班というのがあった。
私は歌謡曲班のマネージャーだったが、コンサート営業の都度、フルバンド用に持ち歩く重たい楽譜に閉口していたのだが、ある日ロック班のプロデューサーに呼ばれ帝国ホテルのロビーに行くと、そこに内田裕也さんがいた。そして今度の沢田研二のマネージャーに任命された者ですと紹介された。僕はコチコチに固まった。それからコンサート最中のジュリーに挨拶に行ったのだが、帰り道「一緒に乗りませんか?」と自家用車に乗り込み、そのまま初対面のその日、僕達は朝まで二人で飲んだのを覚えている。「ああ、遂にロックバンドのマネージャーだ、これで重い譜面からも解放された!」と思ったものだ。
この頃、すでにジュリーの衣装デザイナーには早川タケジ君がいたが、この「恋は邪魔もの」の頃、ジュリーは膝の破れたジーンズをはいていたがあれはジュリーのアイディアだったと思う。今やジーンズの破れファッションは大流行だが、ジュリーがその最初の開祖ではないか。今から40年も昔、破れたジーンズなど履いていたのは彼だけだった。しかも彼は使い古したジーンズをもう一枚短パンのように切り、それを破れたジーンズの上に二重に履くというファッションを考案している。
それで思い出すのは、まだ自分が駆け出しの頃、田園コロシアムのタイガースコンサートの警備につかされた事があった。今やアミューズの会長である大里洋吉君なども一緒だった。その時ジュリーは楽屋で食べ終わった弁当箱の紐を取りだしたので、「どうするんですか?」と聞くと、「こうすると、ちょっと変化が出て面白いでしょう」と言ってそれを首と腕に巻きつけ楽屋からステージに上がって行った。寡黙なのに本当に面白い男だなと言う印象だった。後年、田コロのライブ映像を見ると「ハートブレイカー」などを歌う姿にそれが映っている。
さて、ジュリーは「恋は邪魔もの」を筆頭に「追憶」「カバーオブローリングストーン」などロック色の強い楽曲を引っさげてこの年、ジュリーにとっても、また日本人初の全国縦断ロックツアーを試みた。加瀬さんが演出で私は演助になった。チケットは「恋は邪魔もの」のジャケットの水中眼鏡を形どった変形で、何トンもある楽器車のボディーにそれを描き、楽器車は楽器を下ろした後、会場正面に止めてファンの落書き自由とした。楽器車を動く宣伝カーに仕立てたものだ。
何もかも始まった感がある年だった。ツアーは日比谷の野音でスタートを切り、8月5日には福島県郡山市開成山公園内の総合陸上競技場で開かれたロック・フェスティバルに飛び入り参加。なんと出演者は41組。デビューしたばかりのダウンタウン・ブギウギ・バンド、上田正樹&サウス・トゥ・サウスにキャロル(ついこの前までジュリーのプロデューサーだった中井國二さんが引き連れていた)、それにデビュー前のシュガー・ベイブ、ロンドン帰りの加藤和彦とサディスティック・ミカ・バンド、人気絶頂だった沢田研二ら、当時のロックバンドのほとんどが集結していたと言って過言ではない伝説の郡山ロックフェス。
青春真っ只中、そして、この年7月10日発売されたシングル「追憶」はツアー最中にNo.1を獲得、最大ヒット曲となった。まさに「恋は邪魔もの」はロックスター沢田研二の幕開けだった。
最後に余談だが僕は当時生まれた自分の長男に「貴之」と命名した。「ウチのタカユキが」と言うと井上尭之さんは勿論、ジュリー、バンドメンバーに受けて、祝福されたものだ。
女優木の実ナナさん
その誕生は、苦しみの若き日にそっと応募した越路吹雪「アプローズ」の舞台オーディション合格であったと思う。越路さんこそ、彼女の才を発見、愛してくれた大切な恩人であったと聞く。以来幾星霜。永六輔さん、小沢昭一さん、高倉健さん、先代尾上松緑先生、デスデモーナ玉三郎さんなど多くの先輩、共演者から愛されて、遂にあの伝説の和製ミュージカルの金字塔「ショーガール」の幕が切って落とされたのである。お陰でナナさんのステージを見るといつも側に宮川泰先生がいるように思ってしまう。ナナさんは本当に若者からお年寄りまで幅広い人に愛される女優さんだが、井上ひさし先生、吉行淳之介、詩人田村隆一さんなど多くの作家まで虜にしてしまう魅力。その理由のひとつはナナさんのあの「悲しくとも涙に耐えている」ギリギリの笑顔ー人生への愛ーが生んだ財産だと思う。それが私たちファンに伝播すると、それは明日への希望を抱かせる「勇気」と生まれ変わるナナ魔術なのだ。おっと、忘れてた、ルーツはね「私、ちゃきちゃきの江戸っ子で、庶民派だよ!今は下北が故郷だよ!」
僕個人としてはナナさんのために作らせていただいた曲「道」、今日も聴かせていただけるかな。そして、いつも、いつでも、いつまでも素敵な笑顔を私たちに送り続けて下さい。 ナナファミリーの長き友人として。
昔むかし、ナナさんのお宅に行くと、四人の家族がおりました。それと一匹の仔犬とが。
ちょっと厳格なおばあちゃん、ハリージェイムズというトランペッター好きな、ちょと酒呑みのパパ、明るく優しく気さくで苦労人で、要はナナさんの師匠のママ、恥ずかしがり屋の妹さん。下町風情の人びとでした。
仲間達はこうした人達に育まれたナナさんを見て、みんな木の実家の家族になって行きました。その結果やがて素敵な舞台で、人びとへの勇気と愛のミュージカルスターとなって、女優木の実ナナは大きな夢の花を私達に見させてくれました。
越路吹雪さんをはじめ、永六輔、井上ひさし先生、多くの作家や詩人や役者仲間にも愛され、宮川泰先生が、ナナを取り囲み、やがて不出世の金字塔ミュージカル「ショーガール」も生まれました。その後、大切な人びとも亡くなりもしましたが、それでもやはり永遠のショーガールは今日も歌い続けています。いつも、いつでも、いつまでも、舞台の上のナナさんの素敵な笑顔を浴びて、生きる勇気をもらえるファンが待っているのです。素敵な明日への人なのです。ビバ!ナナさん、日本のジェルソミーナ!
木の実ナナ小伝
春になると富士の山頂(舞台)から幸せの花びらを、この地上(客席)めがけて降り注ぐという伝説の女神コノハナノサクヤヒメ(木花之開耶姫)、まさにその化身、女優木の実ナナさんの誕生は、苦しみの若き日にそっと応募した越路吹雪「アプローズ」のオーディション合格であったと思う。越路さんこそ、彼女の才を発見、愛してくれた大切な恩人であったと聞く。
以来幾星霜、永六輔、小沢昭一さん、映画「大脱獄」の最中に思いで深き誕生日を祝ってくださった高倉健さん、「オセロ」では先代尾上松緑先生に学び、デスデモーナ玉三郎さんと共演。そして遂にあの和製ミュージカルの金字塔「ショーガール」の幕が切って落とされた。お陰でナナさんのステージを見るといつも側に宮川泰先生がいるように思えてしまう。ナナさんは本当に人に愛される女優さんだ。勿論人格が成せる技だが、井上ひさし先生、吉行淳之介、詩人田村隆一さんなど多くの作家まで虜にしてしまう。
どれもナナさんのあの「悲しくても涙に耐える」キュートな笑顔が生んだ財産だと思う。それが私たちファンに伝播すると、それは明日に希望を抱かせる「勇気」と生まれ変わるからだ。
今日もまた、そんな舞台での歌が聴ける。おっと、忘れてた、「私、ちゃきちゃきの江戸っ子で、庶民派だよ!今は下北が故郷だよ」
僕個人としてはナナさんのために作らせていただいた曲「道」、今日も聴かせていただけるかな。そして「いつも、いつでも、いつまでも」素敵な笑顔を私たちにください。





